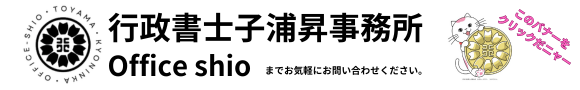富山県内で鋼構造物工事業を営んでおられる社長様、そして工場や現場で高度な技術を発揮されている皆様、日々の業務、誠にお疲れ様です。 ビルや工場、橋梁、鉄塔など、私たちの社会の骨格を創り上げる「鋼構造物工事」。皆様の精密な加工技術と、ダイナミックかつ緻密な現場管理が、安全で強靭な社会インフラを支えています。その社会的責任は非常に大きいものと存じます。
その高い技術力と社会的信用を、揺るぎない形で証明するものが「建設業許可」です。
「うちは鉄骨の組立がメインだけど、どの許可を取ればいいんだ?」 「自社工場で加工もしているが、その場合に必要な要件は?」 「専任技術者になれる資格が多すぎて、どれが当てはまるか判断できない」
このようなお悩みや疑問は、鋼構造物工事に携わる多くの経営者様が抱えていらっしゃるものです。
そこで今回は、建設工事の根幹をなす「 鋼構造物工事」にテーマを絞り、許可取得の最大のカギとなる「専任技術者」の要件について、専門家である行政書士が、基礎からじっくりと、分かりやすく解説いたします。
この記事を最後までお読みいただければ、鋼構造物工事の許可に必要な技術者の条件が明確になり、ご自身の会社が今何をすべきか、その具体的なステップが見えてくるはずです。
「鋼構造物工事」とは?その定義と工事の例
まず、「鋼構造物工事」が建設業法でどのように定められているかを見ていきましょう。
【鋼構造物工事の定義】
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
ポイントは「加工又は組立て」という部分です。鋼材を自社の工場などで加工し、現場で組み立てるところまでを一貫して行う工事をイメージしてください。
- 鉄骨工事(鉄骨の製作、加工、組立)
- 橋梁工事
- 鉄塔工事
- 石油、ガス、水道などの貯蔵用タンク設置工事
- 水門、樋門などのゲート設置工事
- 屋外広告物の設置工事
これらの工事を、1件の請負代金が500万円(税込)以上で請け負う場合、法人・個人事業主を問わず、「建設業許可」の取得が法律で義務付けられています。
《最重要コラム》「とび・土工・コンクリート工事」との違いは?
鋼構造物工事業者様から最も多く受ける質問が、「とび・土工・コンクリート工事との違い」です。どちらの業種にも「鉄骨組立」が含まれており、非常に混同しやすいためです。この違いを理解することが、適切な許可を取得する第一歩です。
- 鋼構造物工事
鉄骨の「製作・加工」から「組立」までを一貫して請け負う工事。自社工場などで鋼材を設計通りに加工する工程が含まれます。 - とび・土工・コンクリート工事
他社が製作・加工した鉄骨を、現場で「組立」ることだけを請け負う工事。いわゆる「現場とび」の仕事はこちらに該当します。
自社の業務実態がどちらに近いかによって、取得すべき許可の種類が変わってきます。もし判断に迷われる場合は、私たち専門家にご相談ください。
絶対に必要!「専任技術者」になるための2つのルート
さて、本題の「専任技術者」の要件について見ていきましょう。 専任技術者とは、「許可を受けたい営業所に常勤し、鋼構造物工事に関する専門的な知識や経験を持つ技術者」のこと。会社の技術力を公的に証明する、許可制度の根幹をなす存在です。
この「専任技術者の要件」を満たす方法は、主に「国家資格」で証明する方法と「実務経験」で証明する方法の2種類があります。
パターン1:国家資格で要件をクリアする
鋼構造物工事の専任技術者として認められる国家資格は以下の通りです。土木・建築・機械と幅広い分野の資格が対象となります。
- 1級土木施工管理技士 または 2級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士 または 2級建築施工管理技士
- 1級建築士 または 2級建築士
- 技術士
- 建設部門(選択科目:鋼構造及びコンクリート)
- 総合技術監理部門(選択科目:建設「鋼構造及びコンクリート」)
- ※鋼製水門等の製作・設置工事の場合、機械部門(流体工学or熱工学)も対象
- 職業能力開発促進法に基づく技能検定
- 鉄工(製缶作業、構造物鉄工作業を含む) / 製缶
・1級、または2級合格後3年以上の実務経験が必要です。
- 鉄工(製缶作業、構造物鉄工作業を含む) / 製缶
《ここがポイント!》
技能検定の2級をお持ちの場合は、合格後に3年以上の実務経験が別途必要となる点にご注意ください。また、技術士の資格は、選択科目まで細かく指定されているため、資格証の内容を正確に確認することが重要です。
パターン2:実務経験のみで要件をクリアする
「資格者はいないが、長年この道でやってきた」という場合でも、道はあります。その豊富な経験を書類で証明することで、専任技術者の要件を満たすことが可能です。
- 学歴不問の場合
- 10年以上の鋼構造物工事に関する実務経験
- 指定学科を卒業している場合
- 大学・高等専門学校の指定学科卒業後 → 3年以上の実務経験
- 高等学校・中等教育学校の指定学科卒業後 → 5年以上の実務経験
《指定学科とは?》
ここでいう「指定学科」とは、土木工学、建築学、機械工学に関する学科です。卒業証明書などで、これらの学科を修了したことを証明する必要があります。
《実務経験の証明こそ、最大の難関》
実務経験で許可を取得しようとする際に、誰もが直面する最大の壁が、この「経験を客観的な書類で証明する」プロセスです。
審査窓口では、口頭での申告は認められず、経験した期間、継続して鋼構造物工事に携わってきたことを客観的な客観的な「書類」で裏付けなければなりません。
- 工事請負契約書
- 注文書と請書
- 請求書の控え(工事内容が明記されているもの)と、その入金が確認できる預金通帳の写し
特に鋼構造物工事の場合、「製作・加工」から携わっていたことを証明する必要があるため、単なる組立工事の契約書だけでは不十分と判断されるケースもあります。工場の加工指示書や材料の仕入れ伝票など、多角的な資料の準備が求められることもあり、書類収集の難易度は他の業種に比べて高いと言えるでしょう。
面倒な手続きは専門家に任せ、社長は本業に集中してください
ここまでお読みいただき、「業種の区分も要件も複雑で、自社だけで対応するのは難しそうだ」と感じられたのではないでしょうか。
社長様の貴重な時間は、元請けとの打ち合わせ、工場の製作工程の管理、現場の安全管理といった、より高度なマネジメント業務に使われるべきです。不慣れな書類仕事に時間を奪われ、本来の業務に支障が出てしまっては元も子もありません。
そんな時こそ、「行政書士」の出番です。 富山県で建設業許可を専門に扱う「行政書士子浦昇事務所」に、その煩雑な手続きをすべてお任せください。
建設業許可は、一度取得すれば安泰ではありません。5年ごとの更新を忘れてしまうと、許可は失効してしまいます。そうした未来のリスク管理も含め、当事務所を会社の法務パートナーとしてご活用いただければ幸いです。
まとめ:富山県の鋼構造物工事許可なら、私たちにご相談ください
今回は、社会インフラを支える「建設業許可 鋼構造物工事」における、「専任技術者の要件」について詳しく解説しました。
- 鋼構造物工事は、鉄骨等の「製作・加工から組立まで」を一貫して行う工事です。組立のみの場合は「とび・土工工事」となります。
- 専任技術者の要件は「国家資格」か「実務経験」の2パターン。
- 認められる資格は土木・建築の施工管理技士や建築士、技術士、技能検定(鉄工など)と多岐にわたります。
- 実務経験の証明には、長期間分の契約書や請求書などの客観的な書類が必須となり、特に「製作・加工」の経験を証明することが重要です。
巨大な鉄骨を組み上げるように、許可申請も一つひとつの要件を正確に、そして着実にクリアしていく必要があります。もし少しでも「難しい」「面倒だ」「自社の場合はどうだろう?」と感じられたなら、それは専門家に相談するサインです。
富山県での建設業許可の取得や更新手続きでお困りの方は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。 お客様の事業が、これからも富山の、そして日本の社会基盤を力強く支え続けられるよう、法務面から全力でサポートさせていただきます。
ご相談やお仕事のご依頼は下のウェブサイトからお問い合わせください!
あわせて読みたい関連記事